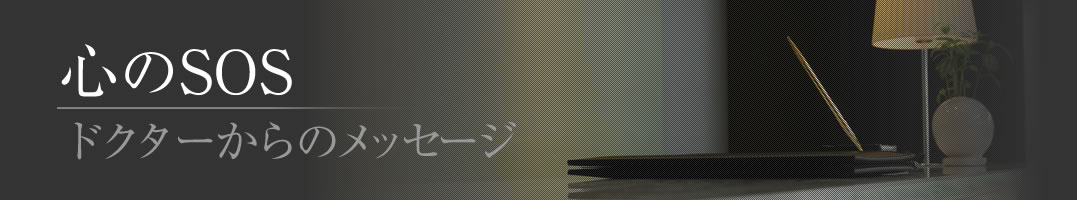精神科の診察室から 精神科医・長岡 和
vol.06
「消えてしまいたい・・・死にたい・・・
「自殺大国」日本のこころの闇」~うつ病
「平成の大合併」と銘打って全国各地で市町村合併が行われている。最終的には全国で地方自治体は3000を下回る数までその数は減少する。平成16年10月1日、浩之が勤務する町役場も1市5町が合併し、新たな市としてスタートを切った。今後、自治体に主体性を持たせた地方自治の方向性は否応なしに押し寄せてきた。しかし、浩之にとっては特別、この合併が大きく自分の生活を変えるとは考えていなかった。何故なら、今までの町役場は新しい市の支所に成るだけで大きな業務変更があるとは考えていなかったからである。しかし、その予測は少しばかりはずれていた。平成16年10月1日に新たな市が発足した後、約3ヶ月毎に人事異動、人事交流が図られ、1市5町の職員たちのシャッフルが行われる事となったのである。また、今まで各市町に於いて組織形態、レポートライン、伝票一枚に至るまで全く様式、形式が異なっていたものが統一を図られ、同じ業務のはずがまるで違う業務であるかの様に思えた。その為、一時的に業務量は増え、対人関係は一変し、否応なしに職場でのストレスは増大し、その変化の波に飲み込まれそうになった。しかし、合併から半年が過ぎて、やっと合併による様々な職場での余波は落ち着きつつあった。
浩之は東京都内の一流私立大学を卒業し、地元の町役場に入った。それは、父親が大手銀行マンであった為に、小中学生の時に幾度となく転居、転校を経験し、本当の意味での「地元」が自分の中で希薄であると共に、何よりも仲の良かった友人たちと分かれる事の辛さから、「自分の子ども達には転校をさせたくない」といった想いがあったからである。浩之は現在39歳。大学を卒業する頃はバブルの絶頂期で就職先は大手企業をはじめとしていくらでもあった。そんな中、町役場に就職を決めた浩之に対して、周りの同期の連中は「もったいない。何で町役場なんかに就職するんだよ。もっと、サラリーの良い大企業からの求人が山の様にあるじゃないか」と怪訝そうな表情で目を向けた。39歳になり、妻である麻美と2人の娘との平凡な生活であったが、浩之は充分幸せを感じていた。当時、怪訝な表情で浩之を見詰めていた同期の連中も最近では「お前の判断が正しかったのかもしれないな。この不況でいつクビ切られるのか、会社が潰れるか解らないからな」と口をそろえて呟いていた。
そんな浩之が体の変調に気付き始めたのは平成17年6月の中旬を迎えた頃からだった。時々、胃がキリキリと痛み、偏頭痛の様な頭痛を自覚する様になった。そして、時には息苦しさや動悸といった症状を認めた。麻美に相談すると「良い機会だから人間ドックにでも入って、キチンとチェックしたら」と促された。人間ドックはやや大袈裟とは想いながらも、近くの消化器内科を受診し、胃カメラ、心電図検査、血液検査等を受けた。しかし、結果、何ら異常は見つからず、健康体であると内科医は説明してくれた。しかし、相変わらず偏頭痛の様な頭痛は続いていた為に、今度は脳神経外科を受診し、頭部CT、MRIを受けた。しかし、これも全く異常所見は見あたらず、頭痛薬を処方されただけであった。
しかし、明らかに体の症状は持続し、最近では食欲も減り、あまり、「食べたい」と思えなくなっていた。そして、2ヶ月のうちに体重は約4kg減少していた。また、痩せたこともあってか全身の気怠さと疲れ易さを自覚する様になった。気が付くとため息をつくことが増え、自然と口数も減っていた。仕事をしていても集中力、注意力に欠け、小さなミスが増え、課長からそのミスを指摘されることが多くなっていた。次第に朝から新聞に目を通すこともなくなり、辛うじて仕事には出て行くことは出来ていた。早朝、まだ、日が昇らないうちから目が覚め、布団の中で何度も寝返りを打った。そして浩之は「消えてしまいたい・・・死にたい・・・」と、まだ家族が寝静まった早朝の闇の中で呟いた。そんな夫の変調を麻美は心配気に観察しつつ、恐る恐る浩之に「一度、精神科とかに言ってみたら?」と投げかけた。浩之は我が耳を疑った。「精神科」その言葉の響きが浩之にとっては何よりもショックだった。「お前は俺が精神病だと言うのか!」つい浩之は声を荒げて、麻美を睨みつけた。普段、温厚な性格の浩之のその言葉と硬い表情に麻美は驚き、それ以上浩之に精神科の受診を勧めることはしなかった。
それから、約2ヶ月が過ぎた頃、浩之はある月曜日の早朝4時半頃、寝室を抜けだし、ネクタイをリビングのドアの取っ手に掛けて縊首自殺を図った。幸いにもその時の物音で麻美が目を覚まし、リビングでぐったりしている浩之を発見した。麻美はその後の事はハッキリとは覚えていない。とにかく、浩之の首に巻かれたネクタイを必死で外し、救急車を呼んだ。そして、小学生の2人の娘と共にパジャマ姿のままでサイレンを鳴らしながら走る救急車の中で浩之の手を握りしめていた。発見が早かった為に、浩之は幸いにも一命は取り留めた。そして、救急救命センターの内科医は後日、精神科の専門病院へ転院することを麻美に切り出した。内科医は浩之が「うつ病」であろうと説明し、キチンと精神科的治療を受けることを促した。浩之はそのやり取りをまるで人ごとの様に、遠い世界の事の様にぼんやりと聞いていた。
9月初旬、浩之は内科医からの紹介状を携えて、麻美に付き添われて精神科病院を受診した。精神科医は今までの経緯を一つ一つ聴いていった。浩之は質問に答えながら、「今からこの精神科病院に入院するのか」と考えるだけで言いようのない不安、いや恐怖と言った方が適切かもしれない耐え難い想いに押しつぶされそうになっていた。そんな、浩之の思いを知って知らずか精神科医は淡々と診察を続けた。そして、浩之と麻美に向かって「うつ病(精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード)」との診断を告げ、WHOが定めた精神科疾患の診断基準なるものを記した1冊の本を提示して、浩之の症状と診断基準が合致することを説明した。その上で今度は、うつ病が脳の病気であること、脳の中でセロトニンを中心とした神経伝達物質が極端に減少し、その神経伝達物質が充分に機能していない事などを説明し、入院の上、抗うつ薬を服用しながら治療を行うことを促した。そして「最後に言っておきたいことはキチンと治療を行えば、充分に回復する病気であり、決して自殺をしてはいけない。これだけは約束して欲しい」と精神科医は語気強めて浩之と麻美に告げた。更に家族の役割としてうつ病に関する正しい知識と理解を持った上で患者に対応することが如何に大切かを説き、「うつ病の家族教室」に参加することを麻美に勧めた。浩之も麻美も精神科医の説明に対してただ頷く他なかった。そして、任意入院となり約3ヶ月後には浩之はこの病院退院するまでに回復していた。
現在、日本では平成10年から自殺者数が年間3万人を超えている。平成16年は3万2325人であった。これで7年連続3万人を突破している。これらの自殺者の3分の2は男性であり、その多くが働き盛りの男性である。そして、自殺する人たちの多くはうつ病をはじめとした精神疾患に罹患していた可能性が極めて高いとされている。また、自殺未遂者の数に至っては自殺者数の20倍とも30倍とも言われている。即ち、年間、100万人近い人たちが自ら命を絶とうとしていて、不幸にも既遂に終わった人たちが3万人を超えているのだ。救急救命センターに搬入される患者の約10%は自殺企図患者であると言われている。また、その自殺の影では年間10万人以上の子ども達が自殺遺児となっている。そして、この自殺遺児をはじめとした残された家族たちには、その後には過酷な人生と現実が突きつけられる。自殺は日本人の死因の第6位である。この自殺が示す数字から日本社会に及ぼす影響、経済的損失ははかりしれないものがある。人口問題研究所の調査研究では経済的損失は少なくとも3兆円を下らないとされている。これは、経済大国日本の一つの大きな影であり、看過できない事実である。今、うつ病をはじめとした精神疾患を如何に早期に発見し、早期に治療に導き、自殺を防ぐかが国の存亡に関わる重大な課題であると言っても過言ではない。「自殺大国」日本は今後どの様に再生を果たしていくのか。そこに求められる精神科医、精神科医療の役割は極めて大きなモノと言えよう。
‹精神科の診察室から›
- Vol.09
- 幻覚体験と被害妄想が平凡な日常生活を打ち砕く~統合失調症
- Vol.04
- 犯罪被害者の苦しみ~外傷後ストレス障害(PTSD)
- Vol.02
- 突然襲い来る死への恐怖~パニック障害~
- Vol.01
- 危険なダイエット ~摂食障害~