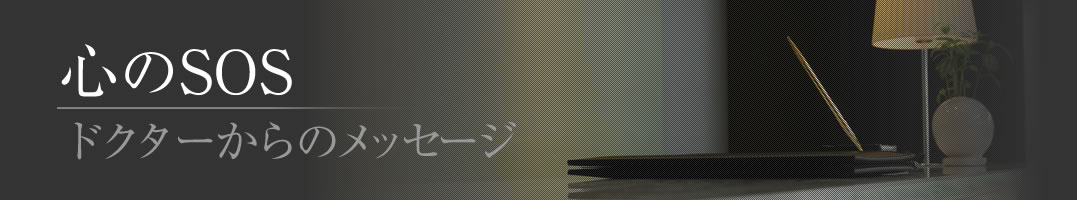精神科の診察室から 精神科医・長岡 和
vol.05 「社会的ひきこもり、ニート・・・人の視線が怖い・・・」~社会恐怖
亮輔は元来、明るい性格で幼稚園に通園し始めた頃から彼の周りにはいつの間にかたくさんの園児達が集まっていた。活発で何処にでもいる普通の元気な男の子だった。そんな亮輔の成長を見守ることは母親である智子にとって何よりも楽しみであり、喜びでもあった。そんな亮輔も小学校に入学。さすがの亮輔も緊張した面持ちで真新しいランドセルを背負い、校門の前で写真に写っている。そして、更にアルバムのページをめくると、運動会や学芸会など様々な学校行事での笑顔いっぱいの亮輔の姿が溢れていた。そして、小学校3年生から所属したサッカークラブで活躍する亮輔のスナップ写真の枚数は数え切れないほどになっていた。学校でも友達は多く、人気者の亮輔。そして、勉強の方も弟の恭輔ほど心配させられた記憶は智子には無かった。亮輔と恭輔は3歳違いの仲のいい兄弟だった。時に勝気な恭輔が亮輔につかみ掛り兄弟喧嘩することはあったが、そこは仲のいい兄弟のことだ。智子の心配をよそにいつの間にか仲直りして、また、何時ものようにサッカーボールをけりあっていた。
智子がそんなことを思い出しながらアルバムをリビングで眺めていると2階の階段から亮輔が降りてくる足音が聞こえた。そして、慌てて智子はアルバムを閉じた。亮輔は智子に一瞥を加えただけでリビングを通り抜け、冷蔵庫からペットボトルを取り出し、そのまま、一気にジュースを飲み干した。その亮輔の横顔は青白く、髪も伸び放題で、うっすらとあごには髭が伸び、その青白い顔色をより一層際立たせていた。そこにいる22歳を迎えた亮輔と今しがたアルバムの中で弾けんばかりの笑顔で写真に収まっていた亮輔が同じ亮輔とはとても思えなかった。
- 智子:「亮ちゃん。お昼ご飯は食べないの?もう2時過ぎよ。」
智子はやや上ずった声でことさら明るい声で亮輔に声をかけた。
- 亮輔:「いらない。」
亮輔はただ一言「いらない。」とだけ言って、冷蔵庫からもう1本のペットボトルを手に取り、スナック菓子の袋をもう一方の手に持って、そそくさと2階にある自室までの階段を上がっていった。そして、程なくバタンとドアと閉める音が智子のいるリビングに響いた。智子の目からは自然と涙がこぼれた。
- 智子:「なぜ・・・こんな風に・・・」
次男の恭輔は今年の春から東京都内の大学に進学し、家を出た。小さい頃は恭輔のやんちゃぶりに智子も頭を悩まされることが多かった。小学校の頃は担任の先生から「恭輔くんは元気でいい子なんですけど、宿題を出してもほとんどやってこないんですよ。お母さんの方からも少し厳しく言ってもらっていいですか。」
- 智子:「恭輔。ちゃんと宿題はしていかなきゃダメよ。ママ、今日、先生からしかられちゃったんだから。」
- 恭輔:「宿題なんかやらなくても大丈夫だよ。今日もテストは100点だったから。」
恭輔はいつもこんな風だった。一方、亮輔は小学生の頃からほとんど注意らしい小言を担任教師から言われた記憶が無かった。いわゆる手のかからない良い子だった。しかし、中学2年生になった頃から亮輔の様子が変わり始めた。朝からなかなか起きようとせず、頭痛や腹痛を訴えては学校を休む様になった。病院に連れて行くが、「特別悪いところはない」と言われるだけだった。中学2年生の2学期からは完全に学校に行かなくなった。と言うよりいけなくなっていた。「不登校」智子の脳裏にそんな言葉が浮かんでは消え、また、浮かんだ。担任の教師にも相談した。スクールカウンセラーにも相談した。当初は友達も心配して朝から迎えにきてくれた。しかし、そのうち自然と友達のお迎えも遠のき、完全に自宅に引きこもるようになった。しかし、自宅では特別、暴力を奮うわけでもなく、家族とは普通に接していた。しかし、生活は不規則になり、完全に昼夜逆転の生活となった。深夜、いや明け方までテレビを見たり、テレビゲームをし、みんなが起き出す頃に床につく生活だ。たまに、外出するときは帽子を目深にかぶり、必ずといっていいほどサングラスをかけて外出した。外出といってもせいぜい近所のコンビニに行く程度で、しかも深夜や早朝といった時刻にしか外出しなかった。必然的に家族以外の人との接触はほとんど無くなった。来客があるとすぐに自室に閉じこもり、挨拶をすることも無かった。そんな生活を続け、中学校の卒業式にも出席しなかったし、当然、高校へも進学しなかった。中学の卒業アルバムは一応担任の教師が自宅まで届けてくれたが、亮輔は一瞥もくれることなく何処かへしまい込んだ。
「不登校」「社会的ひきこもり」「フリーター」「ニート」「パラサイトシングル」そんな言葉が新聞やテレビ番組で一般的に使われ、それらの言葉を聞くたびに智子の胸は引き裂かれそうになった。全ての言葉が今の亮輔に結びついた。そんな時、たまたま立ち寄った本屋で何気なく手にした「ひきこもり」関連の本で精神科への受診を決意した。
そして、嫌がる亮輔を伴って智子は知人から紹介された精神科を受診した。
精神科医は憮然とした面持ちで座っている亮輔に少しずつ質問を投げかけた。最初は頑なな態度を示していた亮輔もゆっくりと思春期を迎えた頃からの自らの変化を語り始めた。中学2年生になった頃から、ひどくクラスメイトの視線が気になる様になり、授業中も常に誰かから見られている感じがして、次第に授業に集中出来なくなったと語る。また、「いつ自分が教師から指名されるのか」「もし、当てられたら・・・」「自分がとんでもない大失敗をしてしまって、みんなの笑いモノになるのでは・・・」等と考えるだけで強い不安感を自覚し動悸、窒息感、振戦、発汗、そして悪寒にも近い様な様々な身体症状を自覚する様になった。そして、実際に指名されると簡単な質問で答えも解っているのに強い不安と緊張から一気に顔から火が出るかの様に赤面し、声は震え、頭の中は真っ白になってしまった。こんな状態が幾度となく自覚される様になったと亮輔は語った。これらの強い不安と緊張、そしてそれから来る様々な自律神経系興奮症状に悩まされ、その結果として徐々に自宅に引きこもる様になった。
しかし、亮輔自身、これらの症状が精神疾患によるモノだとは夢にも考えていなかった。精神科医は亮輔に対して「社会恐怖」との診断を告げた。「シャカイキョウフ」亮輔には不思議な響きの言葉に感じられ、にわかにその精神科医の言葉を信じることは出来なかった。そんな亮輔の動揺を知ってか知らずか、精神科医は淡々とその「社会恐怖」に関して説明し、抗うつ薬や抗不安薬による薬物療法が効果的であること。加えて、認知行動療法と言われる療法を併用して治療を行うことを告げた。亮輔には目の前にいる精神科医が語っていることがにわかに飲み込めなかった。亮輔は今の自分の生活ぶりが病気の症状だと精神科医は説明するのである。確かに、これからの自分の将来や生活のあり様に対しては大きな不安を感じつつもそれが精神疾患の一種であるとは夢にも思っていなかった。最後に精神科医は「ゆっくりと考えて治療を受けるかどうか決めればいい」と言った。
亮輔は悩んだ末、週に一回の割合で通院治療を開始した。そして、徐々にではあったが笑顔を取り戻しつつあった。
「社会的ひきこもり」といった言葉だけが認知されその背景に様々な精神疾患が隠れていることは意外と語られない。ひきこもりの現状を打開する一つの手段として精神科への受診と必要に応じて薬物療法を受けることも一策であろう。
‹精神科の診察室から›
- Vol.09
- 幻覚体験と被害妄想が平凡な日常生活を打ち砕く~統合失調症
- Vol.04
- 犯罪被害者の苦しみ~外傷後ストレス障害(PTSD)
- Vol.02
- 突然襲い来る死への恐怖~パニック障害~
- Vol.01
- 危険なダイエット ~摂食障害~