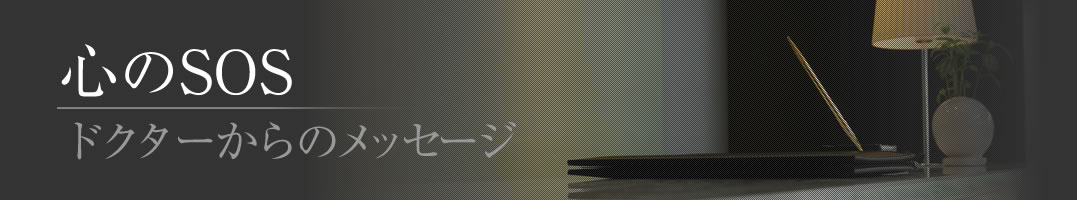精神科の診察室から 精神科医・長岡 和
vol.01 危険なダイエット ~摂食障害~
舞子と里沙は小学校時代からの親友で、学校に行くにも、ショッピングに行くにも、いつも一緒だった。舞子が小学校5年生の時、好きになった男の子に告白するときにも、里沙だけには相談したし、緊張しながら手渡した手紙も、里沙と一緒に書いた。2人はいつも一緒だった。
「里沙にだったら何も隠すことなく相談できる」
少なくとも舞子はそう思っていた。しかし、今振り返れば舞子の様子が変わったのはあの日からだった。あの言葉をきっかけに舞子の中で何かが変わり始めた。
- 里沙:「舞子、もしかして最近、少し太った?」
それは里沙の何気ない一言だった。お互いに何でも言える親友だから、里沙には全く悪気などない。
- 舞子:「ちょっとやめてよね。これでも傷つきやすい17歳なんだから」
舞子は里沙の言葉を軽く受け流しながら、さっき買ったばかりのイチゴクレープを頬張った。すっかり桜の花も散った公園には心地よい初夏の風が吹いていた。そして、2人はいつものようにベンチに座って、日が落ちるまで時間をつぶし、それぞれの家路についた。
- 母親:「舞ちゃん。ご飯よ。早く降りてらっしゃい」
舞子はベッドに横たわって大きくため息をついた。そして、立ち上がり部屋の壁に掛かった大きな鏡に自分を映してみた。
- 舞子:「ちょっと太ったかな…」
公園での里沙の言葉が頭に引っかかっていた。
舞子は身長157センチ。体重は46キロ。今時の高校生としては少し小柄な方だ。それに比べると里沙の身長は166センチと高く、中学時代にはバスケットボールの選手として活躍していた。舞子も何度か里沙の試合を応援に行った事もある。そして、一緒に服を買いに行くたびに試着室から笑顔で出てくる里沙を見ながら舞子は心の中でつぶやいた。
- 舞子:「わたしもあと5センチ身長があったらな」
しかし、そんな舞子も今まであまり体重に関しては気にしたことはなかった。元々、太る体質ではないし、事実、今でも好きなモノを好きなだけ食べてもさほど太った事はなかった。少なくとも太ったと感じたことはなかった。
- 舞子:「やっぱり太ったかな…」
また、鏡の前でつぶやいてみる。
- 母親:「舞子!食べないの!早くしなさい!」
再び母親の少し苛立った声が響く。舞子がリビングへ駆け下りると弟の正樹は既に食事を終えて、テレビの画面を見つめていた。
- 母親:「舞子。どこか具合でも悪いの?」
- 舞子:「何でもないよ!ほっといて!」
母親には悪いと思いながらも、明らかに舞子の言葉は苛立っていた。その日の夕食は半分ほど食べただけで、舞子は早々と自分の部屋に戻った。自分でもなぜ苛立っているのかわからなかった。しかし、あの里沙の言葉だけが何度も頭の中で響いていた。そして、その日はなかなか寝付けなかった。
- 里沙:「舞子。今度、あの公園の裏道においしいケーキ屋さんがオープンしたの知ってる?」
- 舞子:「知らない」
- 里沙:「今日、学校の帰りに寄ってみない?」
- 舞子:「今日はやめとく」
- 里沙:「えーっ。どうして。行こうよ。」
里沙は今までと何ら変わりはない。しかし、舞子は苛立っていた。
- 舞子:「そんなに行きたいなら1人で行けば!」
舞子のあまりの言葉に里沙もびっくりしていた。舞子もそんな自分に苛立ちながら、自然と涙がこぼれてきた。
- 里沙:「どうしたの?舞子。ごめんね。どうしたの?」
- 舞子:「違うの。ごめんね。里沙。ごめんね」
舞子は顔を手で覆い、首を振りながらそれだけ言うのが精一杯だった。
舞子が生理の遅れを気にし始めたのはそれから4ヶ月ほどたった9月だった。今まで3~4日遅れることはあっても、今回の様に2週間も遅れることはなかった。
- 舞子:「わたし、今月、アレきてないんだ」
舞子は学校帰りにつぶやいた。
- 里沙:「アレって生理のこと。まさか。舞子!誰よ、相手は!」
- 舞子:「バカね。そんなことあるわけないでしょ!」
- 里沙:「だよね。舞子に先越されたかと思ったじゃん」
舞子は笑いながら答えたが、里沙の言葉に苛ついていた。
最近、舞子は些細なことで苛ついたり、授業中もボーっとしていることが多くなった。記憶力が落ちたのか、試験勉強をしても集中できず、すぐに疲れた。元々、がんばり屋で几帳面な舞子にはそんな自分が許せなかった。しかし、成績は明らかに落ちていた。「何かがちがう」舞子は特に、体調の不調は自覚していなかったが、徐々に自分の中の変化に気が付き始めていた。そして、明らかに数ヶ月前と違う事が一つあった。体重である。舞子はあの日を境に毎日、朝には体重計に乗り、それをキチンとノートに記録した。そして、朝食はミルクだけと決めた。母親が毎朝準備してくれるお弁当は半分だけ食べて、残りは捨てた。当然、学校帰りのアイスクリームもケーキもやめた。夕食の主食は食べず、肉や魚といったモノはほとんど箸を付けなかった。そして、1日の摂取カロリーをキチンと記録していた。毎朝量る体重が少しずつ減って行く事が嬉しかった。そして数ヶ月前には46キロあった舞子の体重は37キロになっていた。
舞子が母親に伴われて精神科を初めて受診したのは高校3年生になる前の春休みだった。初診時の体重は29キロ。診断は「神経性無食欲症」と告げられた。拒食症である。そして、精神科医からは「今の状態であれば突然死もあります。入院を要するレベルです」とハッキリと告げられた。舞子には診察室で交わされた精神科医と母親のやりとりは遠い世界の他人事のように響いていた。
今、女子高校生や短大、大学生などに「食」に関するアンケート調査をすると、少なくとも10人に1人は食行動上の問題が認められると言われている。過激なダイエット、下痢や利尿剤の乱用、繰り返される自己誘発性嘔吐、無茶食い、気晴らし食い等である。
コンビニに並べられた女性誌を手に取って見ると、必ずと言っていいほど占いとダイエット関連の特集が組まれている。この傾向がいつ頃から定着したのかはわからない。しかし、少なくとも10年以上前から毎月、同じような特集が組まれている。時にはリンゴダイエット、たまごダイエット、そして激辛カプサイシンダイエット等々。その種類と手法はいくつあるのかわからない。しかし、間違いなく言えることは、老いも若きも世の女性たちがダイエットに翻弄され続けていると言う事である。
舞子もちょっとしたきっかけから過激なダイエットへと踏み込んでしまった。そして、わずか1年足らずの間に体重は17キロも減っていたのだ。
精神科の診察室で出会う少女たちの中でも摂食障害の患者は決して少なくはない。そして、確実に低年齢化している。まだ、初潮も迎えていないような10歳の女の子ですら受診することもある。そして、そこには過激で危険なダイエットの実態がある。
‹精神科の診察室から›
- Vol.09
- 幻覚体験と被害妄想が平凡な日常生活を打ち砕く~統合失調症
- Vol.04
- 犯罪被害者の苦しみ~外傷後ストレス障害(PTSD)
- Vol.02
- 突然襲い来る死への恐怖~パニック障害~
- Vol.01
- 危険なダイエット ~摂食障害~