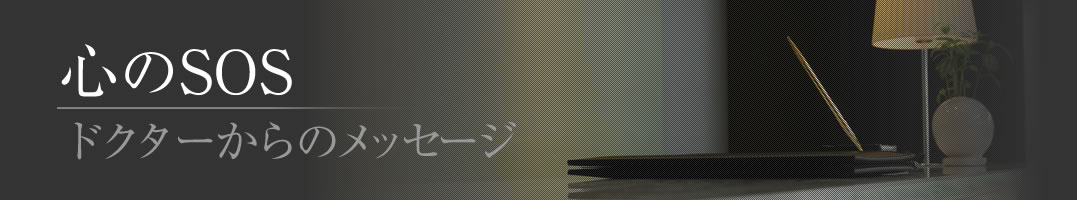精神科の診察室から 精神科医・長岡 和
vol.04 犯罪被害者の苦しみ~外傷後ストレス障害(PTSD)
由紀が親友の美沙に伴われて精神科医のもとを訪れたのは、あの忌まわしい一夜のエピソードから約1ヶ月を過ぎた頃だった。由紀は大学の2年生。現在は19歳で1ヵ月後の12月には20歳の誕生日を迎える。本診(精神科医の診察)にはいる前の段階で行われる予診(看護師や精神保健福祉士等による予備的な情報収集の為の問診)で彼女は主訴(主な訴え、来院理由等)として「男性が怖い」と語っていた。由紀を診察室に招き入れる前に看護師から手渡された真新しいカルテを手にして、一読し、精神科医の脳裏には「おそらく・・・」とある程度の受診の理由が予想された。
由紀は他県の県立高校を卒業し、その年の4月に長崎市内にある女子大の英文科に入学。由紀は親元を離れ初めて一人暮らしをはじめた。今ではすっかり1人暮らしにも慣れ、それなりに楽しいキャンパスライフを送っていた。最初はガランとしていたワンルームのマンションも今では彼女らしいセンスのいいインテリアが配され、シングルのベッドには大きなくまのプーさん縫いぐるみが置かれていた。そんな彼女を悪夢のようなエピソードが襲ったのは暑い夏も終わりに差し掛かった9月のはじめだった。まだ、大学は夏休み中で、由紀は居酒屋でのアルバイト中心の生活を送っていた。居酒屋といっても昼間はランチメニューもあり、昼食時ともなると近くのオフィス街に勤めるサラリーマン達の利用が結構多い。その為、夏休み中は店長から頼まれて朝11時から3時までの4時間と夕方6時からの10時までの4時間とあわせて8時間をアルバイトに費やす毎日だった。そして、あの日もいつも通りバタバタと働いた。金曜日と言うこともあり、いつもより店は込み合い、あがりの時刻は定時の10時を過ぎて11時近くなっていた。由紀は店長に「お先に失礼します!お疲れ様でした!」と元気に挨拶をして店を出た。夏の終わりとはいえ、まだ、生暖かいよどんだ夜の空気と疲れきったせいなのかなんとなく、由紀の足取りは重かった。途中でコンビニに立ち寄り、雑誌とジュースを買った。長崎は坂の多い街だ。由紀のマンションも少し坂道を上がったところにあった。その坂道は昔ながらの石畳で風情はあるものの夜ともなるとやや薄暗く、若い女性のひとり歩きには危険な感じである。
少し薄暗い曲がり角にさしかかった時だった。スッと黒い人影が見えたかと思うと由起の腕をガッチリととらえ、その人影は由起の力では到底抵抗出来ない様な強さで由起を石畳の坂道から少し脇に入った空き地に引きずり込んだ。由起は一瞬、自分の身の上に何が起きたのかわからなかった。あまりにも突然で、一瞬の出来事であることと、その恐怖のあまり由起の頭の中は真っ白になってしまった。そして、その黒い人影はしっかりと由起を羽交い締めにして、一言「騒ぐな!」と低い声で言い、由起の目の前にサバイバルナイフを差し出した。由起は恐怖のあまり声も出すことが出来なかった。それから一連の「行為」が終わるまでの時間がひどく長く、そして、遠い世界の時間の様に感じられた。男は「行為」を終えると「またよろしく頼むよ。お嬢さん」とかすかに笑いながら低い声でつぶやき走り去った。由起はしばらくその場に放心状態で座り込んでいた。しかし、悲しくもなく、悔しくもなく、ただただ涙があふれて止まらなかった。やっとの思いで立ち上がり、泥に汚れ、男の体液に濡れたスカートを見た。一部は引き裂かれていた。
それからどうやってマンションまで帰ったのか全く覚えていない。フッと気が付くとシャワーを浴びながら全身を強く、激しくボディシャンプーで洗っていた。全身の震えは止まらず、おえつとともに溢れ出る涙は止まらなかった。どのくらい、シャワーを浴びていたのかもわからない。その夜はまさに由起にとって悪夢の一夜であった。翌日、体の痛みで目が覚めたのは既に午前10時を過ぎていた。昨夜の事は夢であって欲しいと思いながら恐る恐る体の痛む箇所に目をやった。そこには確かに痛々しいキズとアザがあり、昨夜の事が残酷にも事実であることを物語っていた。
その日は店長に電話してアルバイトを休んだ。しかし、その日を境に由起はアルバイトに出てこなくなった。何度も美沙や涼子からメールがはいる。そして、携帯には無数の着信履歴が残された。心配した美沙が由起のマンションを訪れたのはあの夜から5日が経った水曜日の夕方だった。美沙は何度もチャイムを鳴らし、その後、やっと開かれたドアの隙間からのぞいた由起の顔を見て、全身に悪寒にも似た電流のようなものが走るのを感じた。
美沙「どうしたの!!由起!!」「何があったの!!」
美沙はそう言って由起を強く抱きしめた。今、美沙に出来るのはただそれだけだった。そこにはあの元気な笑顔の絶えない由起とは別人の由起がいた。由起は消え入る様なか細い声であの夜の出来事を美沙に打ち明け、由起の目からあふれ出す涙は止まらなかった。
その後、美沙は毎日の様に由起のマンションへ通った。時には敢えて冗談を言ったり、明るく語りかけ、ドライブに誘ったりした。しかし、由起の様子はあまり変化なく、時々、弱々しく微笑む程度であった。食事もあまり食べることが出来ず、明らかに痩せて頬はこけ目は精気なく落ちくぼんでいった。
由起は促されるままに診察室の椅子に座った。そして、精神科医はゆっくりと由起に語り始めた。まずは自分が精神科医であること、そしてここで語られる事は決して外部に漏れる事はないこと、そして、何よりも男性であるが精神科医であり、彼女の苦しみとこころのキズを出来るだけ早急に治療したいとの主旨を説明した。それらの説明をうつむいて聞いていた由起の目にはみるみる涙が溢れ出していた。そして、少しずつ一連のエピソードについて語り始め、現在の精神症状等に関しても詳しく彼女なりの言葉で答えてくれた。そして、精神科医は由起に対して「外傷後ストレス障害(PTSD)」との診断を告げた。由起はあの夜以来、気分は落ち込み、何もする意欲が湧かないと語り、小さな物音にもひどく過敏で恐怖すら感じ、全身に悪寒の様な震えを認めると語った。睡眠は不規則で一度寝付いても悪夢にうなされ、何度も目が覚める。そして、何よりも男性の姿や低い声を聞くだけで不安と緊張は強まり、震えが止まらなかった。更にはあの夜の悲劇がまるでビデオテープで再現されるかの様に頭の中にありありと映像として浮かび上がり、その恐怖から錯乱状態になってしまう事が何度かあったらしい。いわゆる「フラッシュバック現象」である。
精神科医は由起に対してまずは彼女は被害者であり、何ら落ち度もないこと。あくまでも悪いのはそのレイプ魔であることを強調して伝え、自分を無用に責めることがない様にと伝えた。更に、無理にあの忌まわしいエピソードを忘れようとするのではなく、記憶が徐々に薄れていくことを待ち、その為にも安心して今の苦しみを語れる様に臨床心理士のカウンセリングを受けることを提案した。合わせて、抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤等による薬物療法も行うこと説明した。
性犯罪は非常に事件化することが少なく、ヤミに葬られやすい犯罪である。そして、被害者である女性たちはその苦しみを誰にも打ち明けることも出来ず、心身ともに大きなキズを負い続ける事となる。性犯罪はその他の犯罪よりとりわけ再犯率が高いと言われている。その為、一度性犯罪者が逮捕されると驚くほどの余罪が明らかになるケースが多い。司法改革も含めて、声を上げられない被害者を救いケアする社会的システムの構築が急がれるべきである。
‹精神科の診察室から›
- Vol.09
- 幻覚体験と被害妄想が平凡な日常生活を打ち砕く~統合失調症
- Vol.04
- 犯罪被害者の苦しみ~外傷後ストレス障害(PTSD)
- Vol.02
- 突然襲い来る死への恐怖~パニック障害~
- Vol.01
- 危険なダイエット ~摂食障害~